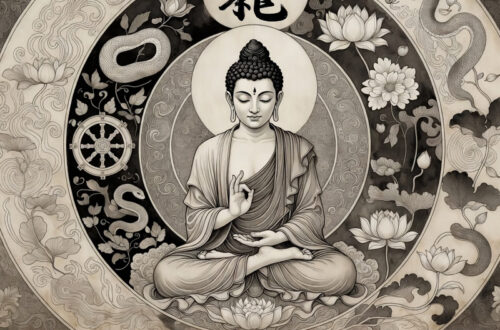勉強をする意味は弱者を救うため
「勉強をする意味は、弱い人を助けるため」
(水元和也)
「勉強って、なんのためにしなくっちゃいけないんだろう?」
と考えている方も多くいらっしゃると思います。
良い高校に入るため?
良い大学に入るため?
良い企業に勤めるため?
年収が良くなるから?
それもひとつの答えかも知れません。
他の答えもあるでしょう。
例えば、
「選択肢を増やすため」
勉強をすればするほど選択肢は増えます。
東大に合格して、医者になったとしても
それ以外の道は無限に拓けてきます。
これも確かに、ひとつの答えと言えるでしょう。
今日、中村哲さんというお医者さんが
アフガニスタンで土木工事をして
砂漠を緑化し村を作ったというお話を聴いていて
思ったことがありました。
この人はこれまで学んできたことを、
自分より弱い人たちを助けるために使った人なんだなぁ、ということです。
これまで、私は
「勉強は選択肢を広げるためですよ」と思ってきたのですが
それでは、結局、
自分に与えられた能力を自分にしか使わないことになります。
これではまだ、egoの支配下です。
私は自分の浅はかさを痛感し、深く反省しました。
まだまだ、知らないことがいっぱいです。
そうではなく、その能力を他人を助けるために使えてこそ
本当に生きた能力になるのではないかと思ったのです。
自己利益のために勉強するのではなく
他者利益のために勉強することも素晴らしい生き方だと思うのです。
「愛」のために勉強するのもカッコイイですよね。
「勉強をする意味は、弱い人を助けるため」
という生き方もアリなのではないでしょうか。
中村哲さんは小さい頃、
おばあちゃんから
「自分より弱い者を助けなくてはならない」
「小さい命でも、命は大切」と幾度となく聴かされ
医師の道を歩みました。
医師になり、
ある時、アフガニスタンの診療所に行きました。
診療所にはケガをした人、飢えた人、感染症の人が多く詰めかけてきました。
新鮮な水が無いせいで
泥水を飲んで感染症にかかり、目の前で亡くなる赤ちゃんをたくさん見てきました。
そこで、井戸を掘りました。
なんと、その数、1600個。
一時的には飲み水は確保されました。
しかし、その後、長期間にわたり雨が降らない日が続き
大干ばつとなりました。
結局は井戸の水も干上がり
畑も枯れ、村人は飢えに苦しみ
仕方なく村を去り、お金を稼ぐために戦争へ行く人が増えました。
貧困と飢えと病気はなくなりませんでした。
そこで中村哲さんは考えました。
「100の診療所より、1本の水路だ!」
「25Km先の川から水を引くために、灌漑用の用水路を作るんだ!」
しかし、アフガニスタンには重機もセメントもありません。
中村医師は考えました。
そして、土木や河川工事を勉強しました。
図面を書くために数学も勉強しました。
日本では江戸時代から使われている
蛇籠(じゃかご)を設置してみたらどうだろう?
蛇籠というのは、竹や鉄線で網を作り、
その中に石を詰めて護岸に設置するものです。

幸いにもアフガニスタンには石ころだけは大量にありました。
村人たちの力を借りて、
みんなで灌漑の用水路を作りました。
村には水と緑が戻ってきました。
農作業ができるようになったので
村を離れていた村人たちも戻ってきました。
多くの人が飢えることが無くなり
病気は減り、
家族みんなで暮らせるようになったのです。
アフガニスタンという、
日本にはなじみのない国。
いつも戦争ばっかりしているというイメージの国。
そんな国の人たちを救った、たった一人の日本人、
中村哲さんは、
自分の能力を、全力で利他的に使って生きた方だと思います。
自分より立場が弱い人のため、
自分より貧しい人たちのため、
自分の知能、能力、頭の良さを使う。
これが、勉強をする意味なのかも!!
と、強く思ったのでありました。

メタ心理カウンセリング
セラピールーム・ソラ